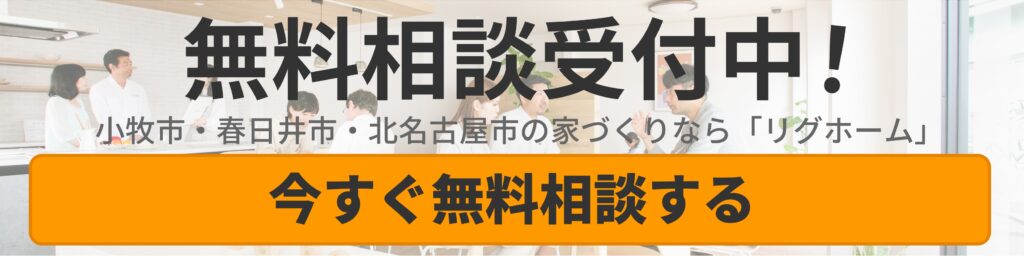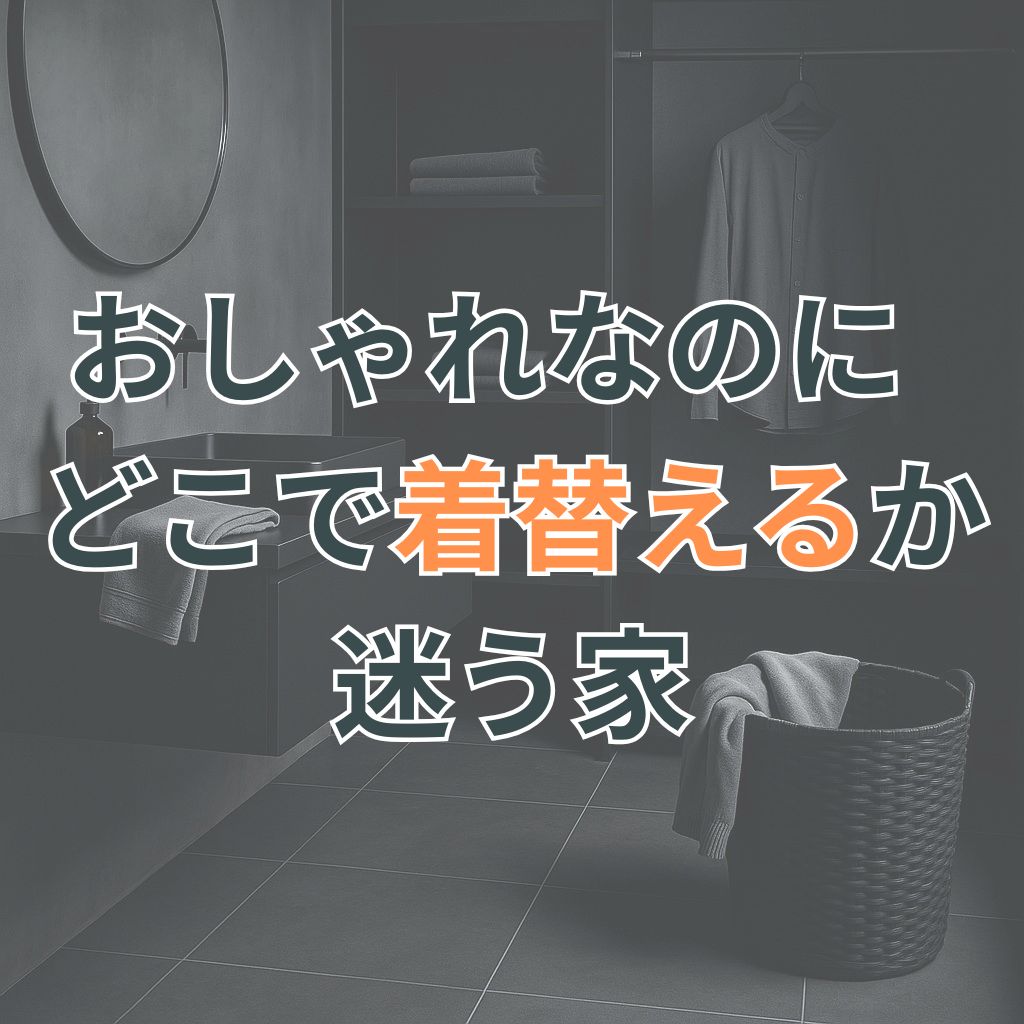
こんにちは、リグホームの山村です。
「洗濯物をたたんでも、すぐしまえない」
「朝の身支度が混雑してバタバタする」
「脱いだ服の置き場が定まらない」
こうした“ちょっとした困りごと”を聞くことが多いのですが、
その原因は間取りや広さではなく——実は、
「どこで着替える?」が定まっていないことかもしれません。
今回は、共働きご家族のリアルな暮らしをもとに、
“着替え動線”から整える家づくりをご紹介します。
✅「洗う・干す・たたむ・しまう・着る」がバラバラ
ある小牧市のご夫婦から、洗面所の動線についてこんな声がありました。
「夜、脱いだ服は脱衣所に置くけど…次の日の着替えは2階のクローゼットでしてるんです」
「子どもは1階で支度するけど、制服は2階。戻る時間がもったいなくて…」
このように、“しまう場所”と“使う場所”が離れていると、
暮らしの中で次のような問題が起きます。
- ■洗濯後、たたんだ服をわざわざ2階まで運ぶ
- ■服の一部が脱衣所に置きっぱなしになる
- ■朝の時間に行ったり来たりが発生して疲れる
間取りの設計段階ではあまり意識されませんが、
「着替える場所」は意外と暮らし全体に影響を与えるのです。
✅“着替える場所”を決めるだけで、動線は激変する

着替える場所は、家族によって違います。
- ■夫は出勤前に2階で支度→洗面所は使わない
- ■妻は洗濯や化粧もあり1階で着替えることが多い
- ■子どもはリビングで着替えることもある
このように、家族全員が“同じ場所で支度していない”場合が大半。
なのに収納は「とりあえず各部屋にクローゼット」というパターンでは、
結局どこに何をしまえばいいか分からなくなります。
洗面所やランドリールームに「着替え収納」があると快適です。
- ■洗濯後すぐしまえる
- ■お風呂→その場で着替えられる
- ■子どもが自分で身支度できる(=習慣化)
あるご家族は「服を階段に持って上がる回数が激減した」と話してくれました。
✅LIGhomeが提案する「暮らしから発想する収納計画」

他社との違いは、「場所」ではなく「行動」から収納を設計する点です。
「服はどこにしまいますか?」ではなく、
「いつ・どこで・どう着替えますか?」とお聞きしています。
- ■朝はどこで着替える?
- ■お風呂あがりは?
- ■パジャマ・部屋着はどこに置く?
- ■着替えた服はその場に置く?洗濯カゴへ?
これらを家族ごとに整理すると、
収納の量ではなく「動きやすい場所」が見えてきます。
実例では、洗面所の一角に「ファミリー着替えコーナー」を設けました。
- ■パジャマ・下着・肌着をしまう浅めの引き出し
- ■制服・体操服・マスクなどの“おしたくセット”エリア
- ■脱いだ服はすぐ洗濯カゴへ→ランドリーへ直行
「声をかけなくても、自分で支度してくれるようになって驚きました」
というお母さんの声が印象的でした。
✅子どもの“おしたくゾーン”が整うと、朝のイライラが激減した話
「朝、何度言っても着替えない」
「制服どこ?って聞かれて探してるうちにイライラ…」
これは、着替えや準備に必要な物が点在していることが原因かもしれません。
■2階のクローゼット
■1階の棚
■ランドセルの中
さらに、「戻す場所」が子ども目線で決まっていないと、
どこに戻せばいいか分からず放置→散らかる、という流れになります。
このご家庭では、リビング横に“おしたくゾーン”を新設。
■制服・体操服・マスク・ハンカチを一式にまとめる
■ランドセル置き場を固定化
■翌日の準備を夜のうちに完了
■引き出しごとに“自分の持ち物”と明確に分ける
「声をかける回数が3分の1になった」
という実感もありました。まさに量より“流れの整理”です。
体操服の脱ぎっぱなし、制服がイスに放置……
こうした問題も、戻す先が設計されていれば防げます。
- ■ランドセル→棚に戻す
- ■体操服→脱衣カゴや洗濯エリアへ
- ■水筒→キッチンへ直行
収納は見た目だけでなく、
“何を、どこに、いつ戻すか”の共有が不可欠です。
✅まとめ|「どこで着替える?」が決まると、家族全体がラクになる
- ■“着替える場所”が決まっていないと、暮らしにムダが増える
- ■子どもが支度できないのは“性格”ではなく“構造”のせい
- ■収納より先に「行動の場所」から逆算するのが効果的
- ■ランドリー+脱衣室+おしたくゾーンで支度がスムーズに
- ■LIGhomeでは「誰が・どこで・どう動くか」を家族全員分ヒアリングして設計する
朝の支度がバタバタしているなら、
間取りや広さよりも“着替える場所”を見直すだけで変わるかもしれません。
LIGhomeでは、暮らしの流れを丁寧にヒアリングし、
動線と収納をセットで設計しています。
収納ではなく、“ラクな流れ”を一緒につくっていきましょう。