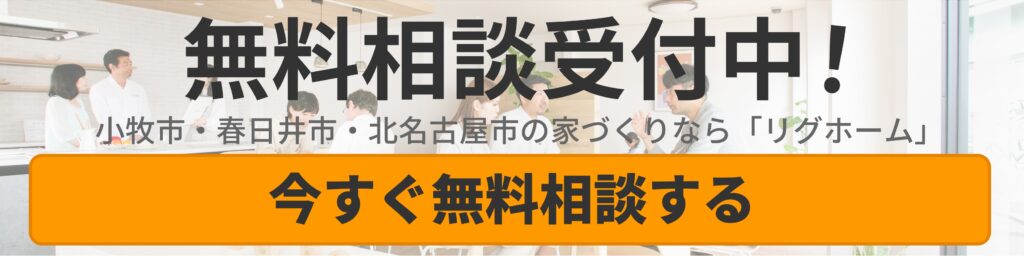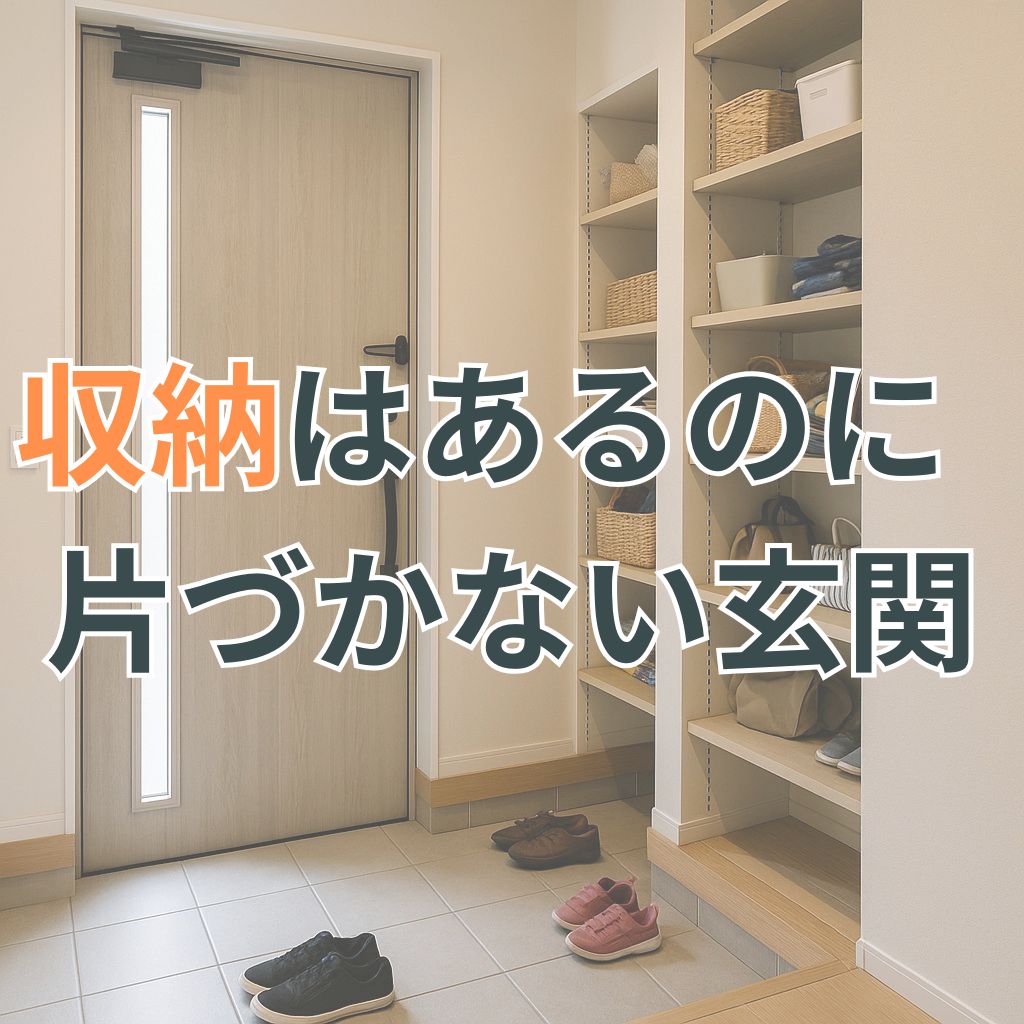
こんにちは、リグホームの山村です。
「収納は多ければ多いほど、暮らしやすくなりますよね?」
これは、家づくりの相談でよくいただく言葉です。
ですが現場では、“収納は多いのに、なぜか物が片づかない”という声が後を絶ちません。
今回は、小牧市の共働きご家族が「収納迷子」から抜け出した事例をもとに、
“収納の量”ではなく“収納の質”が暮らしを左右する理由を掘り下げていきます。
✅収納の「多さ=正解」だと思っていたあの頃
あるご夫婦は、最初の打ち合わせでこうおっしゃいました。
「とにかく収納を多くして、あとで何でも入れられるようにしておきたくて」
「土間収納もパントリーもWICも全部ほしいです。多くて困ることはないですよね?」
たしかに、要望の段階では“多いに越したことはない”ように感じます。
ですが実際に暮らしが始まると…
- ■使わない場所に物がたまりがち
- ■しまった物がどこにあるか忘れてしまう
- ■収納が「遠い」「深い」「奥すぎる」などで使いづらい
「ウォークインクローゼット、奥に入るのが面倒で使わなくなってて…」
これは、ある奥さまのリアルな声でした。
✅収納が「多いのに片づかない家」ができる理由

どこに何をしまうか、暮らしとセットで考えないと意味がない
収納計画でよくある失敗は、「とりあえず大きく・たくさん」設けてしまうこと。
- ■リビング収納が1ヶ所に集中していて回遊できない
- ■土間収納があるのにベビーカーが入りきらない
- ■キッチン横のパントリーが遠くて日用品がリビングに出しっぱなしに
つまり、「収納はあるのに片づかない」という矛盾が生まれるのです。
“量”より“動線・タイミング・使用頻度”がカギ
あるOB施主の例では、玄関収納をあえて分割しました。
- ■靴・傘・ベビーカー:玄関に近い側に
- ■外遊び道具・アウトドア用品:車寄せ側の収納へ
- ■ゴミ仮置きや買い物袋:中と外を行き来しやすい位置に
このように、「いつ・どこで・誰が・何を」使うかで分けると
暮らしの中で“自然に片づく仕組み”ができます。
✅LIGhomeの収納提案は「暮らしを翻訳する」ことから始まる

他社との違い:図面上の「面積」より「動きの質」を重視
収納提案においてLIGhomeが大切にしているのは、
「何をどこにしまうか」の前に、「どう暮らしているか」を伺うこと。
- ■仕事から帰ってまずどこに行きますか?
- ■子どもはどこでランドセルを下ろしますか?
- ■洗濯物は干す→しまう動線はどうなっていますか?
こうした生活行動を先に描くことで、
収納が“暮らしの邪魔をしない場所”に自然と決まっていきます。
実例紹介:収納を減らしたことで、暮らしやすくなった家
「思いきって収納を減らしてよかった。使わない収納って、あっても意味がなかったんですね」
このご家庭では、“収納の場所をしぼる”ことで、かえって行動が整いました。
- ■リビングは「見せる収納+さっと隠せる収納」の2か所に集約
- ■2階の個室には最小限のクローゼットだけ
- ■よく使うモノは1軍だけ“動線の中”に
「前より物が少なくなったのに、なぜか暮らしやすい」
そう語ってくださったのが印象的でした。
✅“すぐ使いたい物”が見つからない家に、足りなかった考え方
片づいているのに、生活が整わない矛盾
収納は整っているのに、こんなお悩みが出ることがあります。
- ■朝の出発に時間がかかる
- ■日用品を買いすぎて在庫が増える
- ■探し物が増えるたびにストレスがたまる
この矛盾を解く鍵は、“収納の場所”ではなく“タイミング”にあります。
「よく使う物」と「すぐ使う物」は違う
収納計画では「使用頻度の高いものを手前に」という考えが一般的です。
ですが、実生活では「タイミングの近さ」がより重要です。
- ■洗剤は“洗濯物を運ぶ瞬間”に使う
- ■ティッシュは“出かける前にカバンへ”が最重要
- ■鍵や財布は“出発数分前”のアクセスが肝
この視点が抜け落ちていると、「動きにくい家」になります。
✅収納は「モノの置き場」ではなく、「暮らしの加速装置」
行動と連動した収納で、生活の流れを最適化
実例では、次のような改善がありました。
- ■ストック類をパントリーに一括せず、使う場所に分散
- ■「入れる→使う→戻す」が同じエリアで完結
- ■ストックは「見える保管」+「使う順」に並べる
結果、「朝の支度がスムーズになった」「探し物が減った」と実感されました。
収納は“分類”ではなく“行動の設計”。
「探さなくても、そこにある」状態を目指します。
✅まとめ|“しまう”より、“取り出す”を基準に
■この記事の要点
- ■収納は「多ければいい」ではなく「使えるかどうか」が重要
- ■片づかない原因は“量”ではなく“動線と目的のミスマッチ”
- ■“すぐ使う物”の配置が、暮らしの快適さを左右する
- ■LIGhomeは行動と動線から収納を設計
- ■探し物が減れば、気持ちと時間に余白が生まれる
■読者へのメッセージ
「収納はたっぷり作ったはずなのに、なんだか使いづらい」
そう感じている方にこそ、“しまう”視点ではなく、“使う”視点からの見直しをおすすめします。
LIGhomeでは、あなたの暮らし方を丁寧にヒアリングしたうえで
収納の「場所」ではなく「流れ」を設計します。
気になる方は、ぜひ一度ご相談くださいね。