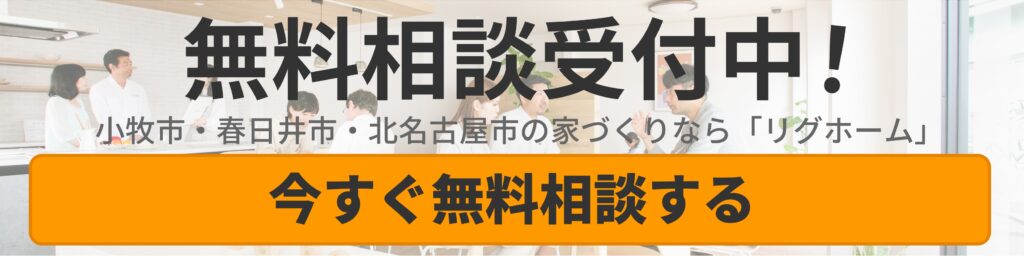こんにちは、リグホームの三浦です。
お盆が過ぎても、まだまだ蒸し暑い日が続いていますね。皆さん、体調崩されていませんか?
今日はちょっと面白いテーマでお届けします。「熱中症」と「巾木(はばき)」の話──。
一見、関係なさそうに見えるこのふたつ。でも実はどちらも、暮らしの“見えない安心”を支えている存在なんです。
✅熱中症が一番多いのは“梅雨明け”って知ってました?

「熱中症って8月がピークじゃないの?」
実はこれ、意外と多くの方が誤解されているんです。
最も熱中症の死亡リスクが高まるのは、実は梅雨明け直後(7月中旬〜下旬)なんですよ。
理由は単純で、体が暑さに慣れていないから。
「暑熱順化(しょねつじゅんか)」という言葉をご存知でしょうか? これは人の体が徐々に暑さに慣れる現象のこと。順応には1〜2週間かかると言われています。
だからこそ、梅雨明けからお盆前後のタイミングは、実は熱中症になりやすい“危険ゾーン”。
私たちスタッフも、夏の現場では必ず「水筒+塩タブレット」持参が鉄則です。
あるお客様とのやりとりで、「家にずっといたのに熱中症になったんです…」と伺ったことがあります。よくよく聞いてみると、「暑くても扇風機だけで頑張っていた」とのこと。真面目な方ほど、節電を意識されるんですよね。
でも、無理して体調を崩してしまったら元も子もありません。
屋内でも油断禁物
特に高齢の方やお子さんがいるご家庭、在宅ワークの方は要注意です。
最近の住宅は断熱性能が高いとはいえ、昼間にこもった熱が夜まで残ることも。ヒートアイランド現象の影響もあって、夜間熱中症も年々増えています。
体感温度を左右する「湿度」
「エアコンつけてるのに暑い…」というときは、湿度が高くないか確認してみてください。
人は、湿度が15%上がると、気温が1〜2℃高く感じるとも言われています。
最近では、温湿度のバランスを自動で感知してくれる便利なアイテムも多く出ていますね。
✅さて「巾木」ってどこにあるでしょう?

ところで、「巾木(はばき)」って知っていますか?
お打ち合わせのときでも、「あ〜、あの床と壁の間の細いやつ?」と、なんとなくご存知の方もいれば、「聞いたことないかも…」という方も。
でも実は、毎日の暮らしの中でひっそりと“守ってくれている”存在なんです。
巾木の主な役割
- ・床と壁のすき間を美しく見せる(施工上どうしても出る隙間をカバー)
- ・ホコリや湿気が入り込むのを防ぐ
- ・掃除機やロボット掃除機が壁を傷つけるのを防止
- ・クロスの端がめくれたり汚れたりするのを防ぐ
- ・冷暖房の空気が漏れ出すのを軽減
最近は「巾木なしですっきり見せたい」というご要望も増えてきました。インテリアへのこだわり、よく分かります。
でも、現場を預かる身としてはこう思ってしまいます…
「なくす前に、ちょっとだけ立ち止まって考えてほしいな」と。
実際、巾木なしで施工したお家で、こんなご相談がありました。
「壁の下が黒ずんできた」「掃除機の先が壁にガンガン当たってクロスが傷んできた」など…。
小さなところだけど、じわじわ効いてくる“守りの役割”なんですね。
✅デザインと機能の“いいとこ取り”、できます
巾木を完全になくすのではなく、たとえば…
- ・壁と同じ色にして目立たなくする
- ・高さを抑えてスマートに見せる
- ・入り巾木にして、壁と一体感を出す
こんな風に“ちょっとした工夫”で印象はガラッと変わります。
そして何より、建築というのは「縁を切る」ことで性能が保たれるものなんです。
たとえば…
- ・コンクリートのひび割れを防ぐ「目地」
- ・排水管の振動を伝えにくくする「緩衝材」
- ・フローリングと壁の接合部に入れる「見切り縁」
全部、「縁を切る」ことで、振動・音・湿気・ひび割れなどを防いでいるんです。
巾木もまた、その一員。小さな存在に見えて、実はとても大事な“縁のバリア”なんですよ。
✅まとめ|体の境界線も、家の境界線も守ってあげること
- ・熱中症のピークは梅雨明け直後。暑さに慣れていない時期こそ注意!
- ・湿度・室温・疲労のバランス管理がポイント。
- ・巾木は暮らしを守る“縁のガード”
- ・デザインと機能の両立も可能。設計段階で相談を
普段あまり意識しないところにこそ、“家の快適さ”は隠れているものです。
健康も、家も、どちらも同じ。
見えにくい部分を、ちゃんとケアしてあげることで、安心と快適が生まれます。
「巾木って気にしたことなかったけど、ちょっと見直してみようかな…」
そう思っていただけたら、うれしいです。
リグホームでは、これから家づくりを始める方向けに無料相談会や勉強会を実施しています。
土地探し・資金計画・間取りの考え方など、どんなことでもご相談いただけます。
「ちょっと話だけでも聞いてみたいな…」という方も大歓迎です。
まずはお気軽に、話すところから始めてみませんか?