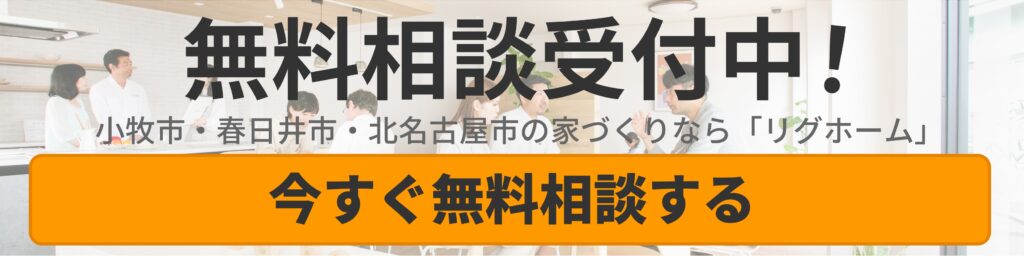こんにちは、リグホームです。
「こども部屋って必要なんでしょうか?」
初回のご相談で、よくいただく質問です。
「まだ小さいから一緒に寝てるし、しばらくは使わないかなと思って…」
「でも、あとで『やっぱりあった方がいい』ってなるのも怖いし…」
そう悩む方は、小牧市でも非常に多いです。
今回は、そんな“こども部屋どうする問題”に向き合ったご家族のお話をお届けします。
✅リビングの横にベビーベッド、が当たり前だった日々

「最初は『リビングの隅で寝かせればいい』って思ってたんです」
そう話してくれたのは、小牧市内にお住まいの共働き夫婦。
当時は1歳半のお子さんがいて、
■ 寝るときは親と同じ布団
■ おもちゃはリビングのカゴに収納
■ 保育園セットもキッチンカウンターの横
という“なんでもリビング完結”スタイルでした。
「夫婦で話しても『個室って必要?』って、なかなか答えが出なくて…」
「広く作っても結局使わなかったらもったいないし、掃除も手間になるし」
そんな悩みを抱えたまま、間取りの打ち合わせが始まりました。
✅個室の“正解”が見えないまま、設計が進んでしまう不安
図面を前にして、ふと奥様が言いました。
「…で、この“子ども部屋A・B”って、いつ使うんですかね?」
設計士が返したのは、よくある定番の説明でした。
「将来2人目ができたときのことを考えて」
「勉強や友達との時間が大事になりますから」
けれど、それって本当に“今の自分たちの暮らし”に合っている?
「なんかテンプレの間取りに当てはめられてる気がして…」
「正直、ピンと来ないまま設計が進むのが一番怖かったです」
これはご家族に限らず、同じような不安を感じている方が多いのが現実です。
✅「つくっておけば安心」は、本当に安心か?
多くのハウスメーカーで見かけるのは、
■ 6帖×2部屋のこども部屋
■ ドアで完全に仕切る個室スタイル
■ 将来的に間仕切りできるだけで、実際は使われない期間が長い
「使うか分からないのに、6帖って必要かな?」
「ずっとリビング中心の生活だったのに、突然部屋にこもられたら寂しいかも」
こんな“心理的距離”の心配も、リアルな声です。
特に共働き家庭では、
■ 一緒に過ごせる時間が限られる
■ 個室にこもることで会話が減る
といったことへの抵抗感が強い傾向にあります。
✅“こども部屋の有無”ではなく“距離感”が焦点だった
最後に奥様がこんな一言を口にされました。
「個室をつくるかどうかより、“どうやってつながるか”の方が気になってるんだと思います」
この一言が、家づくりの本質を突いています。
「こども部屋の有無」は単なる構造の話ではなく、
「家族の距離感をどう設計するか」という“暮らしの核心”なのです。
✅「閉じる」のではなく「緩やかにつながる」個室を
最終的に、このご家族が選んだのは
■ 2階に将来間仕切り可能な子ども部屋スペースを確保しつつ
■ 1階のリビング横に“つながる小空間”をつくるという設計でした。
いわゆる“スタディコーナー”でもなく、
“収納だけのスペース”でもない。
■ 絵本やおもちゃを置ける
■ 子どもが1人で遊んだり、親と一緒に片付けできる
■ 将来、兄妹で使い方を話し合える
そんな「使いながら距離感を育てる場所」です。
✅子どもの変化に合わせて“成長する間取り”

「子どもって思った以上に“段階的に”変わっていくんですよね」
とご主人。
2歳→4歳→6歳と成長するにつれて、
■ 遊びの内容が変わる
■ 1人で過ごす時間が増える
■ でも、まだ不安なときは親のそばにいたがる
こうした変化に「間取りも寄り添っていけることが大切だった」と感じているそうです。
✅暮らしの中で育まれる「空間の使い方」
完成から1年。取材時に印象的だったのは、お子さん自身がその“つながる空間”を気に入って使っている姿でした。
「ここはぼくの場所ー!」と声をあげながら、おもちゃを並べたり、絵本を読んだり。
時にはリビングにいるママに話しかけながら、時には1人で黙々と作業に没頭して。
奥様もこう話していました。
「“完全に閉じない場所”って、安心感があるんでしょうね。『こっちの気配は感じるけど、1人でもいられる』っていう距離が、ちょうどいいのかも」
✅設計打ち合わせで生まれた夫婦の会話
当初、「個室は最低2部屋」と考えていたご主人も、設計が進むにつれて考えが変わっていったそうです。
「よくよく考えると、自分が子どもの頃も“居場所”はリビングだったなって」
「ゲームも勉強も全部そこでしてたし、結局“部屋”って寝る場所だった気がする」
すると奥様も「それなら、リビングの延長みたいな場所があればいいよね」と合意へ。
設計士から提案されたのは、視線が抜ける位置に小上がり空間を設けること。
「完全な和室ではないけど、クッションや収納を工夫すれば多用途に使える」と、自然とその案に惹かれていったといいます。
✅LIGhomeで実践している「つながる設計」の考え方
今回ご紹介したお宅以外でも、LIGhomeでは
■ 子どもが成長しても“気配を感じられる”設計
■ 壁ではなく“視線と動線”で距離を調整する間取り
を多く取り入れています。
たとえば…
・こども部屋の一部に高窓を設け、光と音を通す
・部屋のドアをリビングから直接見えない角度にする
・2階ホールを“ファミリースペース”として広めに確保する
——こうした工夫が「部屋を与えたら終わり」にならない関係性を支えています。
✅あなたの暮らし方に合う“家族距離感”を一緒に探しましょう
「部屋を何帖にするか」ではなく、
「どうつながりたいか」「どんな時間を増やしたいか」
そうした視点を持って家づくりを考えると、間取りの選び方も大きく変わります。
「自分たちの場合はどうだろう?」
「まだ小さいから…でもいずれ成長したら?」
そんな風に迷っている方にこそ、ぜひ一度ご相談いただきたいです。
きっと答えは、部屋の数ではなく“暮らしのイメージ”の中にありますから。